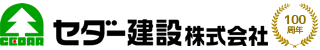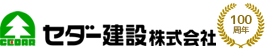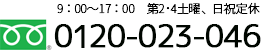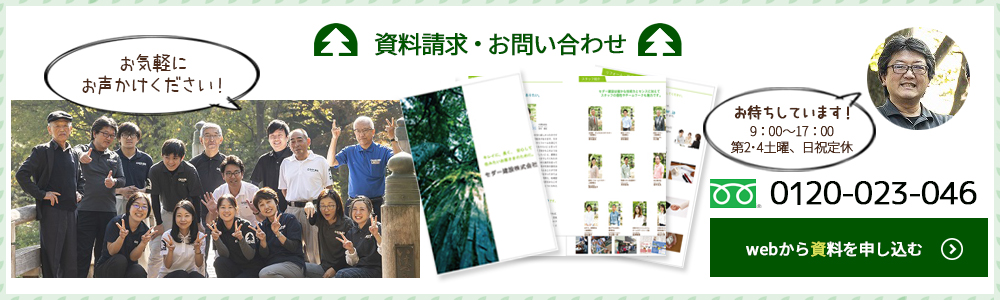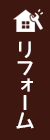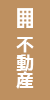令和7年9月11日 上池台の豪雨被害|水害リカバリーについて
(2025年09月12日)セダー建設代表の若杉です。
令和7年9月11日上池台の豪雨で被害に遭われたみなさまにお見舞い申し上げます。
弊社も翌日はご依頼を受けて9件ポンプ活動を回りました。
お困りごとがまだまだあるかと思いますが、なるべく優先度を上げて対応したいと思いますので、お声をかけてみてください。
信州大学で、水害(気候変動適応策の研究)をされている、中谷岳史先生がSNSで下記の情報を公開されていました。
許諾をいただきまして、ご紹介いたします。
被災者の方も・ボランティアの方も、建築業者の方もぜひ読んでください!

↓↓↓ここから
(応急措置1段階目の初動、直後~一週間を目安)
水害リカバリーは、応急措置→計画→復旧工事の三ステップです。
応急措置は、初動→修正→確認の三ステップです。
現在は「応急措置の初動」です。
ボランティアセンターのボランティア派遣までは一週間ほど要します。人手がたりないので、被災地以外からの支援をお願いします。
力仕事だけがボランティアではありません。家事や買い物も災害直後の重要な水害支援です。
▼ 被災者の方へ
1. 建物の撮影
外観は四面すべて、室内は各部屋を撮影する。
水位が分かる写真が重要(保険鑑定人説明や罹災証明に必要)。
2. 荷物の搬出
建物から荷物を敷地内へ出す。
廃棄する物は道路際、その他は敷地内に並べる。
荷物の分別はものすごく大変です。家の外に出すことを優先してください。分別や廃棄物処理場の運搬は外部支援者に頼ることが最適です。
3. 室内の洗浄
泥で濡れた床などに中性洗剤水を散布し、ブラシでやさしくこする。
雑巾ではなく大きなスポンジをつかう。斜めに切ることで三角形になり、隙間を掃除できます。
水切りや流水で泥を押し流す。
4. 床下の乾燥
一か所だけ床下を開け、ダクトファンを土間に設置する。
約1か月間を目安に乾燥させる。
5. 建築業者に連絡(床上浸水の場合)
建築会社に相談し、漏電確認、給湯器・エアコン等の動作確認を行う。また壁内部に水がはいっているか確認してもらう。
6. 保険会社に連絡
建物・車の保険会社に連絡する。手続き、保証金額の把握、代車など、
中学生以下の子供は作業に参加させない(疾患やトラウマのリスクが高いため)。
人と会話をするようにする。被災直後は想像以上にストレスを受けている。
夜は必ず寝る。復旧作業は長期戦になる。
感情が高ぶって動けるように感じても、1週間ほどで肉体疲労が出てくるため、無理をせず他人に頼る。
転倒防止:室内から外までの動線は最初に水で掃除し、必要に応じて廃棄する絨毯や畳を滑り止めとして使う。
サンダルは厳禁。必ず靴を履く。
▼ お知り合い・支援者の方へ
災害廃棄物処理場が開設されたら、敷地に出された荷物の分別と運搬を支援者が行うととてもよい。
▽持参すると良いもの
・滑り止め付き手袋
・マスク
・運動靴
・長袖と長ズボン、または半袖+アームカバー
・中性洗剤(例:キュキュット無香、アタックゼロ)
・10リットル程度のバケツ数個
・水切りモップ
・床ブラシ
・土嚢袋(廃棄物用)
・美味しい食べ物
・飲み水
・安全のための保護具と衛生管理
・切り傷対策:手袋・長袖・長ズボンで肌の露出を防ぐ。
・粉塵・カビ対策:防塵マスクやゴーグルで気道と目を保護する。
・作業後は作業着をビニール袋に密閉して持ち帰り、粉塵が拡散しないようにする。
・作業後は必ずシャワーを浴び、体と髪をよく洗う。
▽力仕事ができなくてもできる支援例
・濡れた食器を洗う
・濡れた衣類をコインランドリーで洗う
・食事の用意や差し入れ
・買い物やトイレへの送迎
▼社協、ボランティアの方々
家の外に出された荷物を、災害廃棄物処理場もしくは一時仮置場所の受け入れがととのった段階で、軽トラックで回収することは有効だと思います
燃えるごみトラック、たたみトラックなど回収品目をきめて巡回することで、効率よく分別できること、また被災地域の特定、応急措置の進行状況の推定ができます。浸水地域なのにあの家は荷物が出されていない、などがわかります。
水害直後一週間は混乱しますので、このタイミングの実施をご検討いただければ幸いです。
▼建築業者さん
なお直後は漏電確認がとれにくいこと、室外機関連は乾かしてから(可能であれば室外機制御盤やファンを洗浄)動作確認なので、災害直後では現場判断がまじります。ただ早いほど住民の自宅避難生活が向上します。また災害直後は応急修理制度は未定、適用されてもエアコンは対象外です。
床上浸水であれば、高い確率で壁体内に水が入っています。壁体内部の診断、必要に応じて壁部分解体を行います。